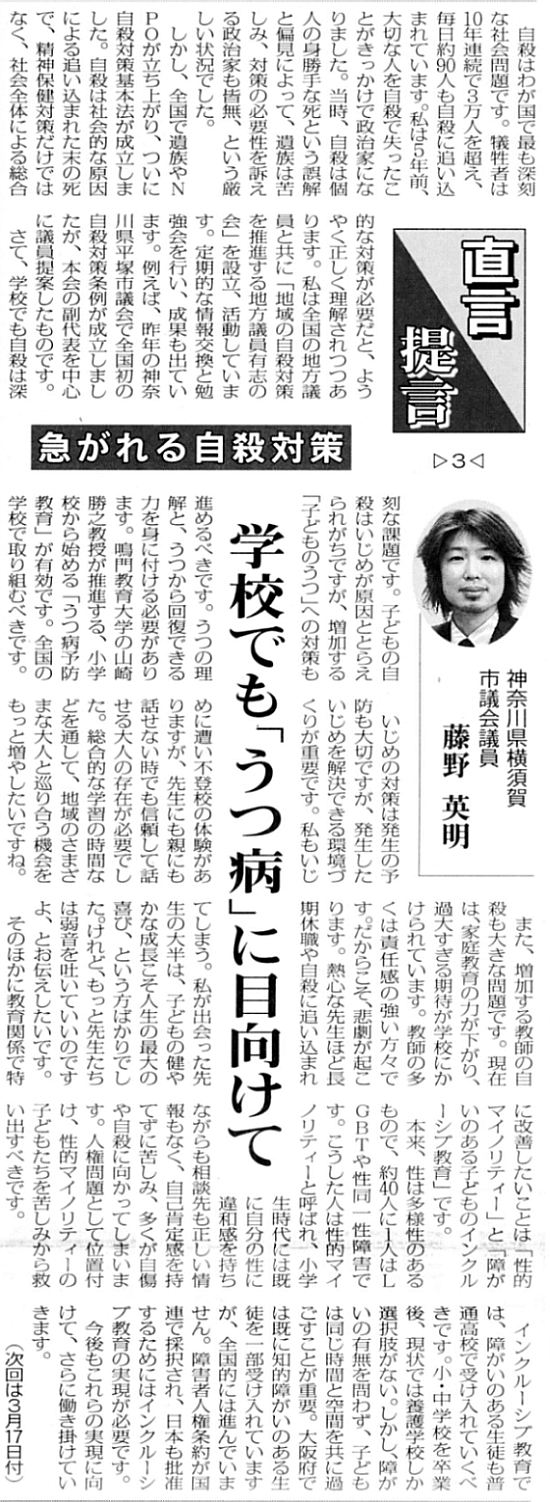日本教育新聞にインタビューが載りました
本日発行された日本教育新聞に、2月26日に受けたフジノのインタビューが載りました。
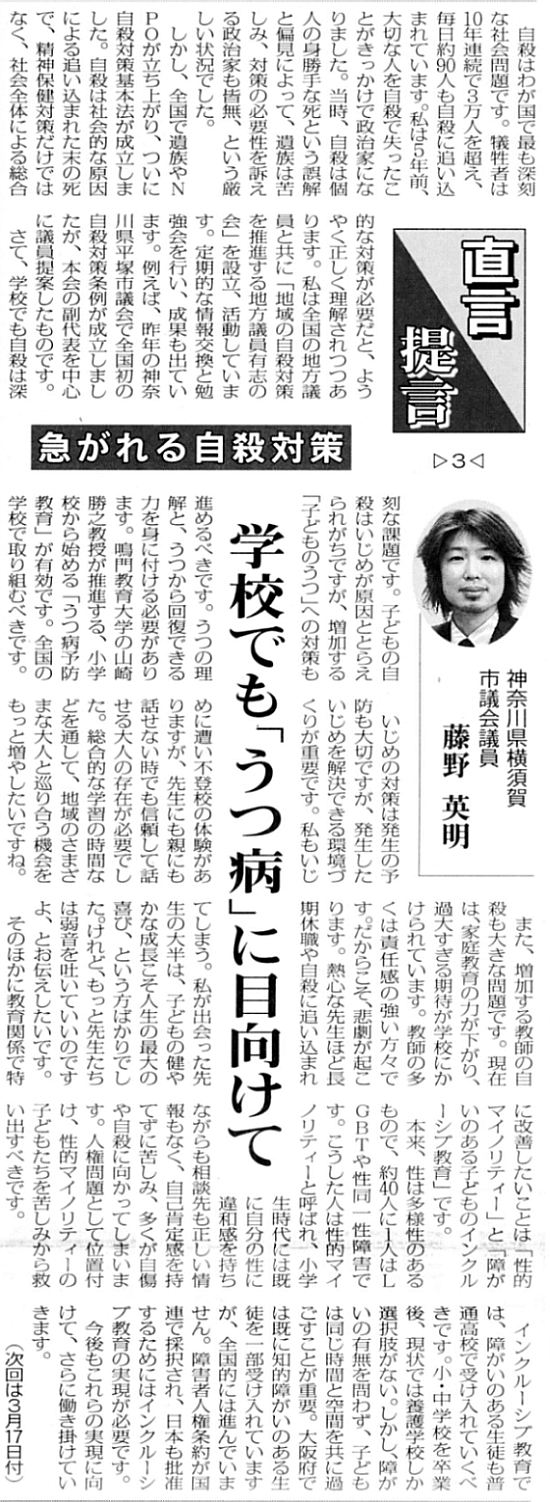
日本教育新聞・2008年3月3日号より
*文字におこしたものは次のとおりです。
『急がれる自殺対策~学校でも「うつ病」に目向けて~』
自殺はわが国で最も深刻な社会問題です。
犠牲者は10年連続で3万人を超え、毎日約90人も自殺に追い込まれています。
私は5年前、大切な人を自殺で失ったことがきっかけで政治家になりました。
当時、自殺は個人の身勝手な死という誤解と偏見によって、 遺族は苦しみ、対策の必要性を訴える政治家も皆無、という厳しい状況でした。
しかし、全国で遺族やNPOが立ち上がり、ついに自殺対策基本法が成立しました。
自殺は社会的な原因による追い込まれた末の死で、 精神保健対策だけではなく、社会全体による総合的な対策が必要だと、 ようやく正しく理解されつつあります。
私は全国の地方議員と共に 『地域の自殺対策を推進する地方議員有志の会』を設立、活動しています。
定期的な情報交換と勉強会を行い、成果も出ています。
例えば、昨年の平塚市議会で全国初の自殺対策条例が成立しましたが、 本会の副代表を中心に議員提案したものです。
さて、学校でも自殺は深刻な課題です。
子どもの自殺はいじめが原因と捉えられがちですが、 増加する「子どものうつ」への対策も進めるべきです。
うつの理解と、うつから回復できる力を身に付ける必要があります。
鳴門教育大学の山崎勝之教授が推進する、 小学校から始める『うつ病予防教育』が有効です。
全国の学校で取り組むべきです。
いじめの対策は発生の予防も大切ですが、 発生したいじめを解決できる環境づくりが重要です。
私もいじめに遭い不登校の体験がありますが、 先生にも親にも話せない時でも信頼して話せる大人の存在が必要でした。
総合的な学習の時間などを通して、 地域の様々な大人と巡りあう機会をもっと増やしたいですね。
また、増加する教師の自殺も大きな問題です。
現在は、家庭教育の力が下がり、過大すぎる期待が学校にかけられています。
教師の多くは責任感の強い方々です。だからこそ、悲劇が起こります。 熱心な先生ほど長期休職や自殺に追い込まれてしまう。
私が出会った先生の大半は、 子どもの健やかな成長こそ人生の最大の喜び、という方ばかりでした。
けれど、もっと先生たちは弱音を吐いていいのですよ、とお伝えしたいです。
そのほかに教育関係で特に改善したいことは 『性的マイノリティ』と『障がいのあるこどものインクルーシブ教育』です。
本来、性は多様性のあるもので、約40人に1人はLGBTや性同一性障害です。
こうした人は『性的マイノリティ』と呼ばれ、小学生時代には既に自分の性に違和感を持ちながらも相談先も正しい情報もなく、自己肯定感を持てずに苦しみ、 多くが自傷や自殺に向かってしまいます。
人権問題として位置付け、 『性的マイノリティ』の子どもたちを苦しみから救い出すべきです。
『インクルーシブ教育』では、障がいのある生徒も普通高校で受け入れていくべきです。
小・中学校を卒業後、現状では養護学校しか選択肢がない。
しかし、障がいの有無を問わず、 子どもは同じ時間と空間を共に過ごすことが重要。
大阪府ではすでに知的障がいのある生徒を一部受け入れていますが、 全国的には進んでいません。
『障害者人権条約』が国連で採択され、日本も批准する為には『インクルーシブ教育』の実現が必要です。
今後もこれらの実現に向けて、さらに働きかけていきます。